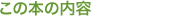定価:1,365円(税込)
整理番号:ト-4-1
刊行日: 1997/09/10
ドストエフスキーは、肉親にも、親友にも理解されることがなかった。批評家には、作品は理解できても、その人柄は理解できなかった。その意味で、ドストエフスキーほど孤独な人間も珍しい。それだからこそ、なんとしても自分自身について語りたい。『作家の日記』は、ドストエフスキーの、このようなやむにやまれぬ気持から生まれた特異な作品群である。第1巻は、1873年に雑誌『市民』に発表したものを収める。
1873年(はじめに
往時の人たち
環境
個人的なことをひとつ
ヴラース
ボボーク
途方にくれたお顔つき
「ある人物」の半書簡
展覧会に関連して
仮装の人
空想と幻想
ある新しい戯曲について
小景
先生
嘘についての一言
現代的欺瞞のひとつ)
定価:998円(税込)
整理番号:ハ-5-2
刊行日: 1997/09/10
原始芸術の萌芽は古代の祭祀の中にある。周期的に催される祭りに、人々は「集団的情緒」を共有し、そこに美を見出した。ギリシアを中心に、東西の祭式と古代美術、考古学、古代社会と宗教との関係を丹念にひもときながら、祭式から芸術への移行過程を探る。芸術の起原を解き明かした古典的名著。
第1章 芸術と祭祀
第2章 原始祭式 無言所作踊り
第3章 季節祭式 春祭り
第4章 ギリシアの春祭り
第5章 祭式より芸術への移行 ドローメノン(「行事」)とドラーマ
第6章 ギリシア彫刻 パナテーナイア彫刻帯とアポルロー・ベルヴェデーレ
第7章 祭式と芸術と人生
定価:1,470円(税込)
整理番号:マ-10-2
刊行日: 1997/09/10
代官山集合住宅、幕張メッセ…60年代から90年代のめまぐるしく移り変わる都市に向かって建物という形で発信し続けてきた建築家・槇文彦。「つくる」ことの豊かな思考によって書かれ洞察された建築とアーバンデザインの論考の数々。内なる異郷としての都市、集合体、コミュニティと建築、パブリック空間の創造…多くの里程標をたどりながら一貫して「都市と建築」の生態的・文化的意味を問い続け、現代の都市のなかにたたずむ建築の美しさを追求しつづけた35年にわたる軌跡、待望の文庫化。
4 アーバン・デザイン―空間の語彙と文法
5 造形と意匠
6 建築家と作品
終章 スケッチ・イメージ・未完の形象
定価:1,365円(税込)
整理番号:マ-10-1
刊行日: 1997/09/10
戦後いち早く渡米し受けたモダニズムの洗礼、グラハム美術財団基金を受けて旅した世界の町々…出生の地・東京への思いを抱きつつ、建築家・槇文彦は比較文明論的な視線のもと建築をそして都市を洞察し続けてきた。「奥」や「すきま」、プライヴェイトなパブリック空間の再発見など、空間のなかに時間と人のたたずまいをよみがえらせる卓抜な都市論。建築の世界に棲み、つくり、そして書きつづけた35年間の著作集、待望の文庫化。
序章 都市とともに
1 モダニズムの光と影
2 私の都市―獲得する心象風景
3 江戸・東京―都市の時間・都市の空間
定価:1,365円(税込)
整理番号:イ-16-5
刊行日: 1997/09/10
それ以前にはなかったもの、そしてそれ以後に生まれてきた諸物万般。明治維新を境として、欧米からもたらされ、現代の私たちの生活の基礎を築いたもの、電気・自転車・化学・哲学・新聞・音楽・会社、また、スキー・ゴルフ・バー・ビール・はじめての洋食の味などなど。いつ、だれが、どこで、いかに考え、そして取り入れ、自分たちのものとしていったのか。エンサイクロペディスト石井研堂が調べつくした、現代日本の文化・文明の始まり。鉄道・人力車・自転車・汽船…、全国の交通網は一気に開け、目に見えて体験できる文明開化の花盛り。円貨・銀行・保健…、新しい商業のために何が必要か。
第9編 交通部(利根と横浜の運河
街道の清新
橋の種々相
人力車の始め
自転車の始め ほか)
第10編 金融商業部(アルレンシヤンド
悪金試験法
井上侯の明治初期財政実歴談
移民会社の始め
伊勢八の没落史 ほか)
定価:1,470円(税込)
整理番号:ロ-2-2
刊行日: 1997/08/07
「小説にはじめて社会諷刺の書というにふさわしい作品が現れた」(本書第23篇「儒林外史」の項)と著者は言う。第24篇では、風俗小説の代表である「紅楼夢」に一篇をあて、内容を詳述し、作品の意義を語る。そして清代流行した武侠物。著者は清末の糾弾小説をもって中国小説の長大な歴史を書き終える。全28篇。この巻では、本書ともっとも関連のある「中国小説の歴史的変遷」および、小論を併載する。
第21篇 明代における宋代市人小説の模倣とその後の選集
第22篇 清代における晋唐小説の模倣およびその支流
第23篇 清代の諷刺小説
第24篇 清代の風俗小説
第25篇 清代の学識と文才を誇示する小説
第26篇 清代の花街小説
第27篇 清代の任侠小説と裁判物
第28篇 清末の糾弾と摘発の小説
中国小説の歴史的変遷
附録 六朝の小説と唐代の伝奇は、どこが違うか
定価:1,470円(税込)
整理番号:イ-16-4
刊行日: 1997/08/07
それ以前にはなかったもの、そしてそれ以後に生まれてきた諸物万般。明治維新を境として、欧米からもたらされ、現代の私たちの生活の基礎を築いたもの、電気・自転車・化学・哲学・新聞・音楽・会社、また、スキー・ゴルフ・バー・ビール・はじめての洋食の味などなど。いつ、だれが、どこで、いかに考え、そして取り入れ、自分たちのものとしていったのか。エンサイクロペディスト石井研堂が調べつくした、現代日本の文化・文明の始まり。文明開化の基礎は教育にあり。知識を世界に求めて生まれ出たさまざまな学校、そして学問。
第七編 教育学術部(浅草文庫
岩倉鉄道学校の始め
アイノ教育の始め
有馬小学校と文明義塾
跡見女学校の始め ほか)
第8編 新聞雑誌および文芸部(悪徳新聞
四十八字新聞紙
一枚摺り新聞の始め
威力を発揮す
一冊一百部と一万部 ほか)
例.「宮沢賢治」→「宮沢」
叢書ウニベルシタス、講談社学術文庫、中公文庫、岩波文庫、ちくま文庫、みすず書房、哲学、思想、人文科学、芸術、美術、算法少女、復刊、悲劇、古本、イーブックオフ、古本市場...