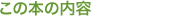定価:1,020円(税込)
整理番号:サ-6-1
刊行日: 1994/11/07
「汚れつちまつた悲しみに/今日も小雪の降りかかる…」。『山羊の歌』『在りし日の歌』のたった二冊の詩集を残し、駆け足でこの世を去った詩人・中原中也。「優しさ」を根に持ち、「悲しみ」と向かいあって歌い続けた、この近代の詩人の作品の底に流れる喪失感の原郷を、「子守歌的なるもの」という視点により鮮やかに捉え直す力作。1988年サントリー学芸賞受賞。
第1章 口語自由詩の本質―亡びたる過去のすべて
第2章 生の氾濫―大正十二年とはなにか
第3章 ダダイズムとの遭遇―喪失の感情
第4章 長谷川泰子と富永太郎―異質な他者
第5章 「朝の歌」まで―陶酔と離別
第6章 『山羊の歌』―子守歌的なるもの
第7章 『在りし日の歌』―詩人のデスマスク
定価:999円(税込)
整理番号:オ-8-1
刊行日: 1994
ページ数:304
江戸期のデカダンスを濃く曳きながら、文明開化による破壊と建設をおこなおうとしていた近代日本。詩人であり、思想家でもある北村透谷は、その知的混沌の不幸を背負いつつ新たな文学の可能性を追求した。近代精神の深い亀裂にみまわれたその作品『楚因之詩』『蓬莱曲』を中心に、評論・随筆、晩年の叙情詩まで、一人の天才の栄光と悲惨、壮大な思考実験の軌跡をたどる。
第1章 アンビションと初期漢詩
第2章 回心
第3章 『楚因之詩』
第4章 バイロンの翳
第5章 『蓬莱曲』(一)
第6章 『蓬莱曲』(二)
第7章 恋愛と風流―批評文(一)
第8章 自然と社会―批評文(二)
第9章 最後の抒情詩
定価:897円(税込)
整理番号:ア-8-1
刊行日: 1994/10/06
一般に言葉とは、思考を表現するものといわれている。しかし、本当に心の中にあるすべてのことを言葉にできるのだろうか。自然の美しさ、恋の思い…言語に絶するこれらを表現するために古来より用いられてきたのが「言葉のあや」=レトリックである。『古今集』などの和歌から現代のコマーシャル・コピーにいたるまで、日本人の言葉の秘密をさぐり、さまざまなレトリックの可能性を論考する。
1 仕立て―仕組まれた場違い
2 見立て―視線の変容
3 姿―見得を切る言葉
4 対句―意味に先立つ形
5 寄物陳思―思いに染まる言葉
6 掛詞―話題の交錯
7 縁語―言葉の連鎖反応
8 本歌取―創造のための引用
定価:1,575円(税込)
整理番号:マ-8-1
刊行日: 1994/09/07
「大衆国家の成立とその問題性」「大衆天皇制論」「〈市民〉的人間型の現代的可能性」「シビル・ミニマムの提起」「市民参加と法学的思考」「国家イメージの転換を」「都市型社会と防衛論争」「組織・制御としての政治」など、大衆社会ついで都市型社会の成熟する中にあって、戦後日本の課題を見定める12の自選論集。自己解題を付す。
1 1956―大衆国家の成立とその問題性
2 1959―大衆天皇制論
3 1960―社会科学の今日的状況
4 1963―池田内閣とニュー・ライト
5 1966―〈市民〉的人間型の現代的可能性
6 1970―シビル・ミニマムの提記(1980)
7 1973―市民参加と法学的思考
8 1977―国会イメージの転換を〔ほか〕
例.「宮沢賢治」→「宮沢」
叢書ウニベルシタス、講談社学術文庫、中公文庫、岩波文庫、ちくま文庫、みすず書房、哲学、思想、人文科学、芸術、美術、算法少女、復刊、悲劇、古本、イーブックオフ、古本市場...