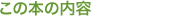定価:999円(税込)
整理番号:サ-9-1
刊行日: 1995/11/07
「取ってね」と「取ってよ」の違いは。「怖いくない」はなぜ問違いなのか。外国人留学生から見ると、日本語はわかりにくいことだらけ。でもそんな疑問をよく考えてみると、ふだん何気なく使っている日本語という言語の意外な特徴が見えてくる。7年間にわたり日本語教師として活躍しきた著者が、留学生たちと過ごした日々のエピソードを通して、教える日本語と日本語教師という仕事をいきいきと語る。アーサー・ビナードとの対談「教える日本語 学ぶ日本語」を収録。
外国人に日本語を教えて(プレイスメント・テスト―プロローグ
クラス始動開始
「これ」「それ」「あれ」「どれ」
「魚がいる」と「魚がある」 ほか)
日本語教師への道(ジャパゆきさん
朴さんからの手紙
日本語能力試験へ
日本語学校のオープンまで
日本語教育能力検定試験について)
定価:999円(税込)
整理番号:ヤ-5-1
刊行日: 1995/10/05
幕末から明治にかけて、西欧文化を受容するために数多くの翻訳語が生みだされた。当時、焦眉の急であった異言語の翻訳をめぐる問題は、とりもなおさず重大な思想上の問題をはらんでいた。たとえば、natureの翻訳語として定着した「自然」は、本当に原語と等しい意味を担いえたのだろうか。その間の意味のずれこそ、日本人の西欧文化に対する「理解」と「誤解」を具体的に指し示しているのではないか。異文化との接触の場所である「翻訳」をめぐる原理的な思考を提示する。
第1章 二つの「自然」をめぐる論争
第2章 辞書、事典に見る「自然」とnature
第3章 翻訳語「自然」が生み出した誤解
第4章 「自然主義」の「自然」とは何か
第5章 自然科学者における「自然」
第6章 丸山真男「自然から作為へ」の「自然」
第7章 「天」とnature
定価:1,529円(税込)
整理番号:ク-5-1
刊行日: 1995/09/07
19世紀のパリは現代社会の先触れである。共和国と独裁制、革命、世界経済、万国博覧会、根なし草になった人びと。第二帝政期の娯楽の王といわれたオペレッタは、市民が公共生活から遠ざかり、私的生活に引き籠るこの社会の浮薄な陶酔状態を、その生きた形姿においてもっともよく捉えた。成り上がり者ルイ・ナポレオンの第二帝政と興隆をともにしたオペレッタの創始者オッフェンバックの伝記を通して、パリの生活を記述する都市の伝記。
プロローグ 時代の真只中に立つジャック
七月王政の黄昏―雌伏するジャック
第二帝政のオペレッタ世界―雄飛するジャック
第三共和政の白けた日々―生き残るジャック
エピローグ ラテルナ・マギカ―すべては過ぎ行く
定価:1,427円(税込)
整理番号:ス-3-1
刊行日: 1995/09/07
悲劇はわれわれに向って、理性と秩序と正義との領域は恐ろしく限られていること、また、われわれの科学や技術の力がどれほど進歩してもこの領域が拡がりはしないことを、教えてくれる。人間の外と内には「他者」が、世界の「他者性」がある。ところが、古代ギリシアのアイスキュロスからシェイクスピアを経てラシーヌまでは勢いがあった、社会生活と想像力的生活とのある本質的な要素―悲劇を生み出す基本的要素―が、17世紀以後は西洋の意識から脱落してしまった。なにゆえに、17世紀は悲劇の歴史における「大分水嶺」となったのだろうか。文芸批評の枠をこえて、近代がもたらした「経験」の変容を活写する。
定価:1,260円(税込)
整理番号:コ-5-1
刊行日: 1995/08/07
ページ数:480
第2次大戦に従軍したひとりの若者が、日本軍の俘虜となり、タイ・クワイ河流域の収容所に送られた。日本人による苛酷な「接待」。不信と憎悪と死臭にみちた生活。アジアを含む膨大な死者を生んだ泰緬鉄道建設の強制労働。収容所という20世紀に現出した地獄のなかで、しかし奇跡的に俘虜たちは、友愛の精神を通して人間性を取り戻す。本書はその、もうひとつの戦いを描いた人間記録である。
死の家
海上で
待っていた接待
死のかげの谷
クワイ河の奇跡
「なんじ我とともにいませばなり」
壁なき教会
クリスマス、一九四三年
チュンカイより、さらに
最後の旅路
谷をすぎゆく
…そして、その後
例.「宮沢賢治」→「宮沢」
叢書ウニベルシタス、講談社学術文庫、中公文庫、岩波文庫、ちくま文庫、みすず書房、哲学、思想、人文科学、芸術、美術、算法少女、復刊、悲劇、古本、イーブックオフ、古本市場...